もう旧サイトの閉鎖まであと1日となってしまったので、片っ端からコピー&ペーストしていきます。1997年の日本帰国時に書いたものですから現在とは状況がかなり異なっていることをご了承ください。
クラシック音楽コンクールがある /Abril en Tarija 1997
このクラシック音楽国内コンクールは1992年より始められ今回で第5回となります。賞品は毎回変わって第1回のギターコンクール優勝者にはイベリア航空よりスペイン留学のための往復航空券(これに優勝したオスカル君はその後マドリッドの国立音楽院で修士課程を卒業しました。)
第2回目ではベネズエラのアリリオ・ディアス国際コンクールに参加、第3回ではウルグアイのエドワルド・フェルナンデスに師事するためにウルグアイ留学など優勝者のレベルもなかなかのものです。
私はこのコンクールにいつも関わっていて課題曲を決めるなどしてきましたので参考までに97年度の課題曲は(小中学生の部、高校生の部、成人の部とありますのでここでは成人の部をご紹介します。)
1次予選
Baxa de contrapunto(L.de Narvaes) La Rosa(M.Giuliani) Mazurka en sol(F.Tarrega)
本選
Tombeau sur la morte de Logy(S.L.Weiss) Estudio No.3(Villa-Lobos) Opcional(次のグループの中から選択)
次の作曲家郡の中から一人を選び10分以内の自由曲を演奏する。
J.Turina,M.Torroba,J.Rodorigo,M.M.Ponce,M.C.Tedesco,A.Lauro,L.Brouwer, A.Barrios,A.Carlevaro,A.Tansman,R.S.de la Maza.
1次予選は例年に習ってルネッサンス、古典、ロマンの各時代の作曲家から選びました。
ちなみに去年は1にはムダーラの牛を見張れ(ナルバエスのではない)、ソルのメヌエット、メルツの愛の歌でした。
2次予選はバロックと近現代の課題曲と自由曲(といっても制限を設けていますが)。去年はバッハのパルティータ1番よりサラバンドとブーレ、ファリャのドビュッシー賛歌でした。
(このコラムは1997年に書かれたものです)
国立の音楽学校がある。
ボリビア国ラパス国立音楽院
Domicillio:6 de Agosto,esq.Azupiazu,La PAz,Bolivia TEl:591-2- caslla:#
幼児コース、中級コース、上級コースがあり、中級、上級とも4年制で学科は弦楽器、管楽器、声楽、ピアノ、ギター、打楽器、作曲学科があり、私はギター学科の主任教授を務めていました。
ギター学科の生徒数は約100人で主任教授高田元太郎のほか2人のボリビア人教授(うち一人は私の生徒)そのほか8人のアシスタントで100人の生徒を教えていました。
ギター科では他の学科と共通の理論教科のほかに実技は毎週独奏2時間、室内楽1時間、オーケストラ実習2時間が必修となっています。
私が教授として赴任中に3人卒業生がでました。1人はオスカル・ペニャフィエル君で卒業後スペインはマドリー国立音楽院に留学しましたが1年で修士課程を修了しボリビアに帰国しました。
現在はラパス音楽院で教授を務めています。その後上級コースの修了試験を終えた生徒が2人いて彼らはオーケストラとギター協奏曲を競演して初めて卒業証書が手渡されます。
皆さんの参考のために私の作った(私の勉強したモンテビデオ音楽院の物が雛形になっていますが)上級4年のカリキュラムをお見せしたいと思います。
次の各グループより1曲ずつ全5曲を演奏。
ルネッサンス
涙のパヴァーヌとファンタジア7番(ダウランド)、オルランド伯のバレーとサルタレロ(モリナーロ)、ファンタジア20番(ミラン)、オ・グロリオッサ・ドミナによるディファレンシア(ナルバエス)
バロック
バッハの4つのリュート組曲かプレリュード、フーガ、アレグロより1組曲選択
古典
ロッシニアーナ1曲か英雄ソナタか大序曲(ジュリアーニ)、大ソナタ(パガニーニ)、ソナタヘ長調(ディアベリ)、グランソロか幻想曲1曲かソナタ作品25番(ソル)
近代(セゴヴィア・レパートリー)
南のソナチネかソナタ3番か主題、変奏と終曲(ポンセ)、ソナタ(トゥリーナ)、ソナティナ(トローバ)、スペイン風3つの小品(ロドリーゴ)、ソナタボッケリーニ讃(テデスコ)
現代
ソナチネ(バークレー)、タラントスか黒いデカメロンかソナタ(ブローウェル)、ノクターナル(ブリテン)、5つのバガテル(ウォルトン)、ソナタ(ヒナステラ)、3つのテントス(ヘンツェ)、5つの小品(ピアソラ)、組曲(エテュ)、すべては薄明の中に(武満徹)
このほかに練習曲7曲:ヴィラ・ロボス2番3番、ジラルディーノ、ブローウェル20番、ソル、ジュリアーニなど
次の作曲家の協奏曲から1曲選択
ロドリーゴ、テデスコ、ヴィラロボス、ポンセ、ブローウェル
(このコラムは1997年に書かれたものです)
クラシック音楽の作曲家/ボリビアのクラシック作曲家達
ボリビアにもクラシックの作曲家はいます。
如何せん、現代曲を書いてもその曲を演奏できるレベルの高い演奏者がいなかったりまた作曲してもボリビア音楽界では出版できない(楽譜の出版社がない)などの理由であまり目立った活動はなかったのですが、ここ数年の演奏家のレベルの向上、作曲家がマッキントッシュなどのコンピューターを自分で持つことにより自費出版が可能になった、などの理由でかなり活発な活動を始められるようになってきました。
また年に1回行われる、現代音楽祭も彼らの創作意欲を高めているようです。その中でも僕が関わった作曲家達は
アルベルト・ビジャルパンド
彼はボリビアでもっとも影響力のある作曲家で多くの若い作曲家達は彼の教えを受けている。1995年にはボリビア初のオペラを初演するなど、なかなか意欲的な活動を行っている。私は1996年にヴァイオリン、チェロとギターのための三重奏曲を初演した。(ボリビアの音階やリズムが使われていて興味深い。)
セルヒオ・プルーデンシオ
ボリビアの若手作曲家の中でもっとも世界的に有名な作曲家であろう。ボリビアの民族楽器を使ったオーケストラ(Orquesta de los instrumentos nativos)を指揮し、またそのオーケストラのために数々の曲を作っている。(Canto de Tierra,canto de vientoは有名)最近は映画音楽も手がけていてボリビア映画”Para Recibir Canto de los Pajaros”の映画音楽はヨーロッパの映画音楽賞を受賞した。(すみません。なんていう賞か忘れました。)女流歌手エマ・フナロと組んだ彼の最新作は今年の3月に発表された。(私はその中の5曲でギターを担当した。)
ハビエル・パラード
ビジャルパンド門下での期待株。彼が1995年に作曲した「ギター独奏の為のアワイニン(高田元太郎のために)」は第1回ラパス市作曲コンクールにて第1位を受賞して2000ドルの賞金を獲得した。そのほかギター関係では”Salto al Alba paraduo de flauta y guitarra”(高田元太郎とアルバロ・モンテネグロの為に)を1996年に作曲。この2曲は今年発表されるCD、”Obras de Javier Parrado”にて聴けるだろう。(カントゥス・プロドゥクシオン)
アルバロ・モンテネグロ
作曲家としての名声より、フルート演奏家、サックス奏者として有名。彼の亡き父親は前在日本ボリビア大使ワルター・モンテネグロ。桐朋音楽大学に留学。彼の在籍するフォルクローレフュージョンバンド「アルティプラーノ」は有名。彼の作曲した六重奏曲「ソニロキオsonoloquio」はCD「ラテンアメリカのフルートとギターのための音楽」(アルバロ・モンテネグロ&高田元太郎)で聴かれるだろう。(クラシック、フォーク、エレキギターとサックス、フルート、サンポーニャのための)
その他にホアン・シーレス、ヘラルド・ジャネス、ウィリー・ポサーダス、オスカル・ガルシア、マヌエル・モンロイなどがよい仕事をしているがそれらについてはまた今度。
(このコラムは1997年に書かれたものです)
興味深い文献が保存されている。
ボリビアのバロック音楽
皆さんが高校や中学で音楽史を学んだりしたときにバロック音楽の作曲家としてでてくる名前は バッハ、ヘンデル、ヴィヴァルディなどで南米の作曲家はでてこなかったと思います。
ではその時代に南米には全く作曲家は存在しなかったのでしょうか。
答えは否です。
コロンブスによるアメリカ大陸発見以前にも原住民たちは彼らの言葉、宗教、文化に基づく音楽を楽しんでいました。
そこへスペインからの移民たちが南米大陸を訪れ2つの文化が初めて接したわけです。
その文化交流はもちろん音楽の面でもあったわけで、とりわけキリスト教の普及のために音楽は用いられました。
そのとき作曲されたミサ曲、受難曲、カンタータなどがつい最近になって何人かの音楽学者らによってボリビアのコンセプシオンやスークレなどで 発掘されました。
それらの音楽はヨーロッパのバロックのように洗練された物ではありませんが、強烈なリズムを持ったり、またスペイン語だけでなく、ケチュア語などの原住民の言葉によってかかれているものもあり とても興味深いものです。
僕のボリビア滞在中にポーランド人のPiotr Nawrot という音楽学者と組んで彼の発掘したボリビアバロック音楽の再生の仕事を行いました
僕は演奏会で通奏低音のパートを受け持ったわけですが、それらの音源はCDとなって残っていて皆さんがボリビアへ 旅行の際には是非購入されるとよいと思います。
Discography
Musica de Visperas en las Reducciones de Chiquitos-Bolivia(1691-17679(CANTVS,CA-002-2)Obras de Domenico Zipoli y Autores Anonimos Editadas y Transcritas por Piotr Nawrot Beatriz Mendes,soprano Susana Valda de Aranda,contralto Pablo Aranda,tenor Coral Nova-Orquesta de Camara de La Paz Ramiro Soriano Arce-Director
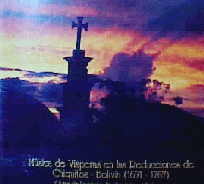
Barroco en Bolivia,Musica de Navidad vol.1(CANTVS,CA-003-2) Obras de Sebastian Duran,Roque Ceruti,Juan de Araujo,Diego de Casseda,Blas Tardio de Guzman,y Autores Anonimos Editadas y Transcritas por Piotr Nawrot Coral Nova-Orquesta de Camara de La Paz Ramiro Soriano Arce-Director
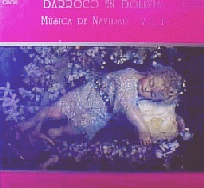
Alabanzas a la Virgen(Misas y Villancicos de los Archivos de Bolivia)(K617,France) Arichivos de Bolivia:Misiones de Chiquitos,Catedral de La Plata(Sucre)Obras trnscritas y editadas por Piotr Nawrot
・Misa Mo Sabado- Anonimo AMCh,038
・Tota pulchra- Anonimo ANB,722
・Stella caeli- Anonimo ANB,705
・Misa Encarnacion- Anonimo AMCh,032
・Quien llena de armonia las esferas?- Juan de Araujo ANB,887
・Parabienes,zagalejos -Juan de Araujo ANB,872
・Hola!Hao!ah!de las sombras- Juan de Araujo ANB,850
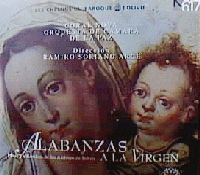
1er.Festival de Musica Barroca-Misiones Chiquitos(CANTVS,CA-006-2)Coral Nova y Orquesta de Camara de La Paz Lirica Colonial Boliviana Coro Polofonico Universitario Coro Juvenil del Instituto de Bellas Artes y Orquesta de Cuerdas “Santa Cruz” Coro y Orquesta Juvenil”Urubicha” Sociedad Coral Boliviana Coro Santa Cecilia
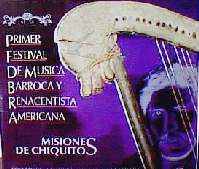
4枚とも演奏はCoral Nova & Orquesta de camara de La Paz/Direccion:Ramiro Soriano Arceです。
ちなみに私は3枚目と4枚目で通奏低音を担当しています。
上の4枚中3枚はボリビア盤なので日本の輸入CD店では入手困難ですが、フランスのレーベルK617は店によっては取り扱っているところがあります。
そのK617の「バロックへの道」というシリーズでは中南米バロックのおもしろいレパートリーが取り上げられています。
その中でもアルゼンチンのグループ「アンサンブル・エリマ」は上記のボリビアのバロック音楽を多数録音しています。それらは
Lima-La Plata/Missiones jesuites
Vespres de lAssomption
Messe de lAssomption de la Vierge
Domenico Zipoli/Vespres de San Ignacio
Juan de Araujo Ensemble Elyma
ところで私の疑問ですが現在ボリビアに存在する楽器のチャランゴやスークレギターなどの起源は何なのでしょうか。
今申し上げたとおり私はボリビアのバロック音楽の通奏低音を担当したわけですが(1)何の楽器を使うべきか(2)どのような奏法が様式にかなっているか、についてかなり悩みました。
これがヨーロッパのバロック音楽であるならばかなりの文献が残っていて例えばテオルボを通奏低音として使うべきだとか、またその時代にもっともあった即興演奏についての凡例などもあるわけです。
しかしバロック時代にヨーロッパにあった楽器が南米にもあったかということは研究しなければ解らないことですし、チャランゴやスークレギターの構造を見ているとリュート、テオルボといったバロック時代の撥弦楽器の構造を踏襲した楽器というよりは、むしろルネッサンス時代のスペインの楽器、ビウエラやバロックギター ( または単純にギターと呼ばれた4コースの楽器)が発展していった形なのではないかという気がしてなりません。
コロンブスの南米大陸発見以降スペイン人達がキリスト教布教のために音楽という手段を執ったおかげで今我々はその楽譜を手にすることができたわけですが、その後ヨーロッパで発展していった音楽界の情報が全く南米に入っていかなかったとしたら、それ以降の音楽と楽器の発展は自由に南米人の感性にまかされてしまったとしたら、南米のバロック音楽演奏は今通説とされていることが全く通じない世界なのではないでしょうか。
もしこの辺についてよく知っている方がいたら是非メール下さい。また私はこう思うという推測でも結構です。
僕のたどり着いた考えはまずスペイン人はスペインのルネッサンス時代の楽器は持っていっただろうけれどその後新しい楽器は持ち込まなかった。
それ故音楽もルネッサンス様式をひきずったものがたくさんあるし、それ以前にあった土着の音楽の影響を受けてかなりリズミックなものではなかったか。
バロック音楽とはいえ持ち込まれたバロックギターなどを伴奏に使っていたのではないか、その際の演奏法は彼ら南米人によって改良され今のチャランゴのラスゲアードを多用する奏法が生まれたのではないか、ということなのです。
以上が僕の推測ですが、これを立証するかのようにK617(フランスのCDレーベルでバロックへの道という南米バロックのシリーズを発売している)からでているアンサンブル・エリーマのアラウホを演奏したCDではビウエラやバロックギターでチャランゴのような奏法を行っていてとても興味深いです。
ちなみに通奏低音は僕と同門フェルナンデス門下のエドワルド・エグエス(現在スイスにてホプキンソン・スミスの助手を受け持っています。)が弾いています。もし手に入ったら聴いてみて下さい。
1996年にボリビアで開催された南米ルネッサンス・バロック国際音楽祭について知りたい方はここをクリック
(このコラムは1997年に書かれたものです)
クラシックCDのレーベルがある。
レーベル
CANTVS produccion
director:Gustavo Navvare Ribera
Av.Strongest #100 Achumani ,La Paz Bolivia
tel:981-2-710004
(このコラムは1997年に書かれたものです)
バロック音楽国際フェスティバル
Festival Internacional de Musica Renacentista y Barroca Americana
”Misiones de Chiquitos”
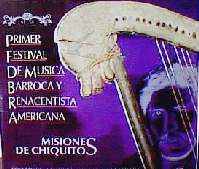
去る1996年4月13日から23日まで第1回南米ルネッサンス・バロック音楽国際フェスティバルがボリビアのコンセプシオン、サンハビエル、サンタクルスにて開かれました。
そのフェスティバルの目的はパンフレットの序文に書かれていますが、それをここに紹介します。
「その音楽がチキートスで聴かれるようになったのは丁度チキターノの混血文化の過程が始まった1961年の終わり頃、サンフランシスコ・ハビエール教会にてでした。
イエズス会の宣教師と土着のチキターノ民族の特別な感性が結びつき、音楽を村人達に文化を与える手段に替えたのです。
そこでは音楽家達(といっても教会の音楽隊にはいることを許されたインディオ達だったわけですが)はそのコミュニティーにおけるエリート達ともいうべきグループを作っていきました。
おのおのの礼拝堂は一般的に40人の音楽家達からなる楽団を持っていて、彼らは礼拝の儀式が改宗者達にとって特別に輝かしく、魅力的な儀式となるように演奏をしたのでした。
この布教のための音楽の適用は宗教的に素晴らしい結果を残したのみならず音楽的価値も素晴らしいものが作り上げられました。
重要なことはこれらの音楽についての豊富な資料は幸運なことにインディオ達の修道院(そこではチキートスで熱心にチキターノの人々によってチキターノ民族のために演奏されてきたのです)やカソリック教会によって保存されてきたということです。
これらの音楽的国宝を保護し、広める目的でこのMisiones de Chiquitosと呼ばれる国際音楽フェスティバルは生まれました。
このフェスティバルを2年ごとに開催することによってその音楽を世に広めるだけならず、それらの音楽を実際に演奏されていた美しく保存されている教会によって聴衆にその教会芸術も知ってもらいたいのです。」
同パンフレットにはPiotr Nawrotのボリビアのサンラファエルとサンタアナ教会に残る音楽手稿譜の資料についての記述が掲載されています。その翻訳文も紹介すると
「ボリビアの古文書保管室に保管される植民地時代の音楽は次のように多様で異なった要素を持つものに区分される。
1)ヨーロッパの作曲家によって、若しくはボリビア土着民族によって作曲されたルネッサンス、バロック様式の音楽。
2)先植民地時代の土着音楽(それらは大体において口頭にて伝えられたのであろうがその後のヨーロッパ音楽にもそれらの影響が見られる場合がある。)
3) 黒人音楽。(これも前の例のようにほんのわずかな譜面を除いて口頭により伝えられた。)
4) そして最終的に今取り上げたすべての要素の融合されたもの。
宣教師達は音楽、踊り、手工芸術に対する原住民達の適応性を見抜き、キリスト教の布教のために有用な道具として芸術を用いました。
それらの資料の最も簡単な研究によってさえ、ほとんどの作品が聴衆の内面に届くメッセージを含んでいることが判ります。そのメッセージがより透明で魅力的なものとなるため、作曲家達は豊富な音楽様式を用いて作曲をしました。
資料の中には豊富なレパートリーが見られますが、その中には、アカペラの合唱曲、単声、複声部の合唱曲、独唱、2重唱や他の編成の曲があり、それらのテキストはラテン語、スペイン語、ケチュア語、アイマラ語、チキタノ語、モホ語、グアラニー語など多様です。
チキターノ達に対するイエズス会の8回の派遣(1691ー1767)によって土着民の音楽形成の発展の度合いは加速されていき、1767年の派遣中止までの間にチキートスのサンタアナとサンラファエル教会には膨大な量の、作曲家達と写譜家達によって残された手稿譜のコレクションができあがっていた。総体的に見てその音楽は宗教的な内容を持ち、教会の毎日の礼拝などに使われていた。
またそのコレクションには器楽曲のレパートリーも見られる。(一般的に南米で発見されたレパートリーは合唱曲が中心である。)イエズス会の宣教師の時代とその次の世代に見られる声楽曲や器楽曲は主に前期バロックの様式が用いられている。レパートリーの様式がヨーロッパのその時代の様式を適用しているのを、インディオ達がヨーロッパ人のまねをしたのだといっては不公平であろう。
それというのも、多くの作品は実際にヨーロッパに生まれた作曲家が作ったものであり、音楽教育や楽器制作術も宣教師達が旧大陸から持ってきたテクニックを採用したものである。
しかしながらそれらの教育を受けた原住民達が作曲したものも多く、特筆すべきはそれらを唱ったり演奏したのは紛れもないインディオ達であり、礼拝や社会的行事に使用された楽器群はインディオ達によって製作されたものであった。
古かろうが、新しかろうが、教えられたものであろうが、採用されたものであろうがそれらは他の宗派のように強制的に布教されたものではなくカトリック教会の普遍性として理解すべきであろう。
(このコラムは1997年に書かれたものです)
ウルグアイ情報
皆さんウルグアイっていう国知っていますか?
旅行ガイドブックでもほんの少ししか取り上げられていないので、南米に旅行されても素通りしてしまう方が多いのでは。
地球の歩き方などでは改訂版がでるたびに減ページとなり、情報も全く更新されていません。
そこで4年間ウルグアイにすんだ経験を頼りに少しウルグアイ旅行ガイドなどというものをしてみたいと思います。(ちなみに私が住んでいたのは1989年から1992年の4年間。情報が少し古いのはご勘弁を。
ウルグアイはブラジルとアルゼンチンに挟まれた小さな国で文化、言語、習慣は基本的にアルゼンチンのそれと変わりません。ただアルゼンチンより物価は安く、とても静かなので僕はモンテビデオに4年間住んでいてとても快適に過ごしました。
それでは住むのではなくて観光するのによい国かというと?です。それでも僕なりによかったなあと思う場所、事柄、店などを書きます。
まずどのように入国するか
ですが、アルゼンチン経由、ブラジル経由の便が多いようです。もしアルゼンチンから行かれるのであればブエノスアイレスからウルグアイに入るとよいのでは。
行き方は3通りあり、ラプラタ川をフェリー、ホバークラフトか飛行機で渡るかで時間、値段が変わってきます。
会社名はそれぞれ順にBUQUEBUS,ARISCAFO,LAPAで、値段はB<A<Lですが、さほど変わりません。
どれも30ドル前後といったところでしょうか。時間は5時間、3時間、2時間半です。
それぞれブエノスからラプラタ川を各手段で渡ってColonia県に着くとそこからはどの会社でもバスでモンテビデオまで2時間です。お勧めはコロニアに着いたらすぐバスに乗らずコロニア市内観光をされたらどうでしょう。
スペイン統治時代の建物が建ち並ぶきれいな町です。
モンテビデオに着いたらホテル探しをしなければなりませんが、安くあげたければユースホステルなどどうでしょう。ユースはスペイン語でAlbergueといい住所はcanelones935です。
それ以外ならツーリストインフォメーションがカガンチャ広場(plaza cagancha)にあるのでここで聞くとよいでしょう。
簡単な地図ももらえるはずです。地球の歩き方(旧版)にでているホテルは要注意。
REXやDiagonal、Nuevo Savoyなどは連れ込みホテルと化している。HOTEL Rio de la Plata(18de julio 937)は安かった覚えがある。(友達のサッカー留学生が住んでいた。)
食事はまともなレストランには行ったらどこの国でもそうですが、高くつきます。
しかしどこのcalle(通り)の角にもカフェテリア(barという)があり、そこで軽食が食べられます。軽食といっても大食いのウルグアイ人にとっての軽食なので、日本人には満腹になります。
お薦めはChivito。これはいわばステーキバーガー。ウルグアイではハンバーガーよりポピュラーな食べ物です。
どこのbarでもそれぞれ味を競っていますが、僕の一押しはLa Pasiva(plaza independecia)のChivito canadiense。Pasivaはチェーン店で16 de Julio沿いに何件もあります。
昼のメニューには、パスタ、ミラネサ、カルネなどいろいろあり僕は一人暮らしの時そばに住んでいたこともありいつもここで食べていました。
あとパスタならRuffinoというイタ飯屋(San Jose entre Yi y Micherini)も高いけどお薦め。あと夏の暑い日ならBarの外のテーブルで生ビール(Chopp)とホットドッグ(pancho)という組み合わせもウルグアイ人には欠かせません。もちろん屋台でチョリパンも結構です。
さて腹ごしらえをしたら少し観光しましょう。
plaza independenciaを境にしてciudad vieja(旧市街),ciudad nueva(新市街)と分かれていて、旧市街に入ってすぐのcalle sarandiには骨董品屋、宝石屋、画廊が並びます。
(ウルグアイは骨董品で有名なのです。)2角歩くと広場にでてここにはカビルドや大聖堂(バリオスの有名なギター曲の大聖堂はここ。)などの建物があります。
その2角下のrincon通りをさらにすすむとBanco de republica があり、これも立派な建物です。さらに突き進むと港の市場(mercado del puerto)があり、市場の中でparillada(バーベキュー)をやっているのがなかなか迫力があり、ここは是非とも写真を撮っていただきたい。
もちろんお肉も安く食べられる。(カウンターで食べるのがよい。)どこのレストランでもそうだがテーブルに座るとcubiertoと称してパンがでてきていくらか取られる。カウンターだとなし。(ボーイを呼ぶときは上品にセニョールなどと呼ばずに大きな声でMozoと呼ぼう。)港は普段立入禁止だが日曜日は入れる。
plaza independencia に戻ってそこから大通り(16 de Julio)沿いはショッピング街や映画館街である。ejidoとの角に市役所ビル(intendencia municipal)がありこのビルは別名panoramicoと呼ばれていて、エレベーターで屋上まで上れてモンテビデオ市内が一望できる。(入り口はSan Jose通り沿い)。
centroを離れても見所は多い。ramblaと呼ばれる海岸通りは一見の価値がある。plaza independenciaを海岸まで下りてそこからずっと歩くのもオツなものである。
20分も歩くとParque Rodoという遊園地がある。その中のロックンロールというのはおもしろいよ(怖いけど)。
centroから121番、116番などPositosと書いてあるバスに乗るとポシートス海岸にでれる。(ハイソサイエティーの若者達はこのあたりにたむろする。)
買い物したい人はさらに116番(だったと思う)に乗ってMontevideo Shopping Centre に行こう。大きいデパートで、マクドナルドも入っている。Lokotosのempanadaも美味しい。
あと書き忘れたけれど、barでpizzaと頼むとチーズなしで来るからご用心。
チーズ付きはmuzarella(ムサレーラ)という。ウルグアイ人はこの何も具のないピザを好む(というより安いから)。さらに腹を太らせるためfainaというお好み焼きの具なしのようなものとピザを重ねて食べることもする。
Feria。この単語は蚤の市を指したり、野菜市場を指したりだが基本的には路上市全般を指すようだ。
もっとも有名なのは Feria de Tristan Narvaja。日曜の午前に calle tristan narvaja を中心に開かれ骨董品、古レコード、衣服、肉、野菜何でもそろう。
この通りは平日でも骨董品屋や古本屋があるので行ってみるとよい。演劇が好きならteatroもある。Feria de Villa Biaritz。このFeriaは前のものよりいくらか高級品が売っている。
これは土曜日の午前に開かれる。116番に乗って20 de Setiembre esquina Ellauri で降りる。(アクセサリーを売っているコロンビア人を見つけたらそれは僕の友達です。)その他もしウルグアイのもっと貧乏人向けのFeriaを見たければ、Feria de Piedra Blanca に行くとよい。(106、169番など)ガラクタが売っている。
モンテビデオ以外にもよいところはたくさんある。
モンテビデオからブラジル方向にバスに乗ればピリアポリス、プンタデルエステ、ロッチャなど素晴らしいリゾート海岸である。ピリアポリスのHotel Argentina は一泊50ドルで食事付きだった(1991年の時)。
温水プールもある。灯台のある丘は絶景。ここからプンタデルエステに行く途中にCasa Pueblo という、芸術家の家があり、バルセロナのガウディの芸術品を思わせる作風である。中にも入れて美術館になっている。(ちなみにこの芸術家の息子が例のアンデス人肉事件の生存者。)プンタデルエステは南米のビバリーヒルズと呼ばれる別荘地。夏はアルヘンティーナスであふれる。
これらの地域には COT社のバスに乗ること。pza.indep.から出ている。他にもSalto県には温泉があるとかいろいろありますが、ちょっと遠いです。
ブラジルに行くにはTTL社のバスで8時間。20ドル程度。(ポルトアレグレまで)。足を延ばしてサンタカタリーナやフロリアノポリスに行くのもいいでしょう。
パラグアイにはバスで14時間程度30ドルだったと思う。(rondeau y mercedez)。まだ書ききれないこともありますがとりあえずこの辺で。Buen Viaje!
PD(追伸)
1)plaza independencia をソリス劇場の横を一角下りたらmercado central がある。そこでタイミングが良ければ鯛の尾頭付きが安く買える。さしみにするとgood。そのmercadoの横にMolini というレストランがありますが、お金があるならば入ってもいいかも。その向かいのパブFun Fun では週2回タンゴの生演奏を夜にやっている。Buenos Aires の San Termo 地区のようにあか抜けてはいないが、観光客向けでない tanguero verdadero にお目にかかれる。
2)コンサート。モンテビデオではクラシックの演奏会が毎日のように場所を替え行われている。Teatro Solis,Alianza Francesa,Teatro Angulo etc 。もしクラシックに限らず他のコンサート、ディスコ、レストラン、映画などの情報を知りたければキオスクで小冊子Guia del Ocio を買えばよい。ウルグアイ版ぴあ?
3)モンテビデオの路線バスはかなり複雑だがこわがらずに乗ろう。線により通るcalle、停留所が違うので要注意。pasaje(乗車料金)は乗ってすぐ切符売りのお兄さん(guardaという)に払おう。(運転手にではない)。降りるときはhay que chiflar(口笛を吹こう)CHiiiiiii o Zuuuuuuu o lo que sea。それでもドアが開かなければpuerta!と叫ぼう。
4)Mate.アルゼンチンのようにマテ茶はとても重要な飲み物。知り合いができたら回しのみに挑戦しよう。ウルグアイ人のマテ好きは有名で歩きながら、バスの中、運転しながらいつでもtermo(水筒)を抱えて飲んでいる。マテセットはcalleで売っていてよいおみやげになるのでは。
5)おみやげといえばmano de uruguay という店が高級手工芸品を売っていて毛のセーター(buzoという)などgood。前期のショッピングセンターやcalle Buenos Aires をplaza independencia から3角歩いたところにある。他にはmercado de artesania がplaza cagancha にある。ここはもう少し安い。
6)montevideo の名前の由来はマゼランが初めて来たときポルトガル語で「我、山を見たり」(Monte vide eu)と言ったことから始まった。そのマゼランの見た山は実は山でなくて丘でCerro と言う。モンテビデオ市内が一望できるので行かれたらどうですか。バスでCerro行きに乗ってもよいがあのあたりはスラム街なのでタクシーの方がよいかも。
7)futbol はEstadio Centenario に行く。2大人気チームはPenarol とNacional。マテを飲みながら観戦すればあなたはもうuruguayo。
(このコラムは1997年に書かれたものです)



コメント